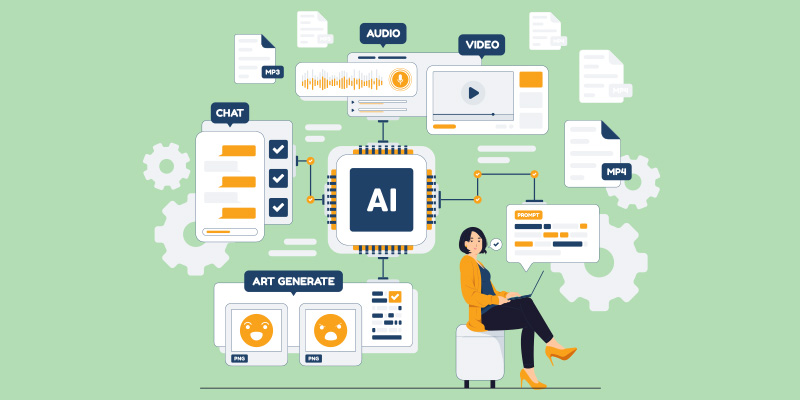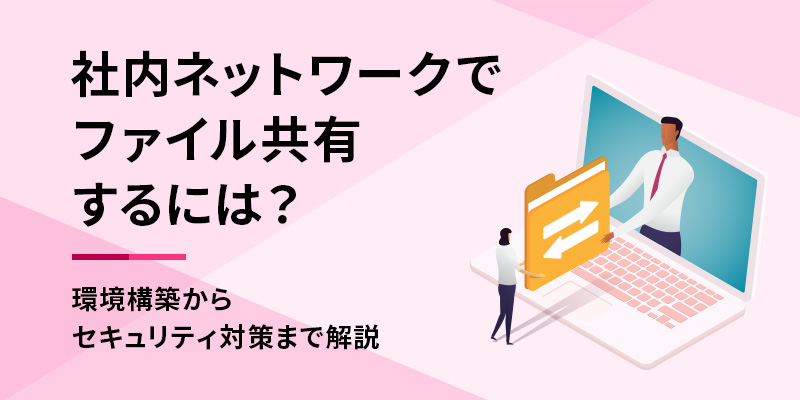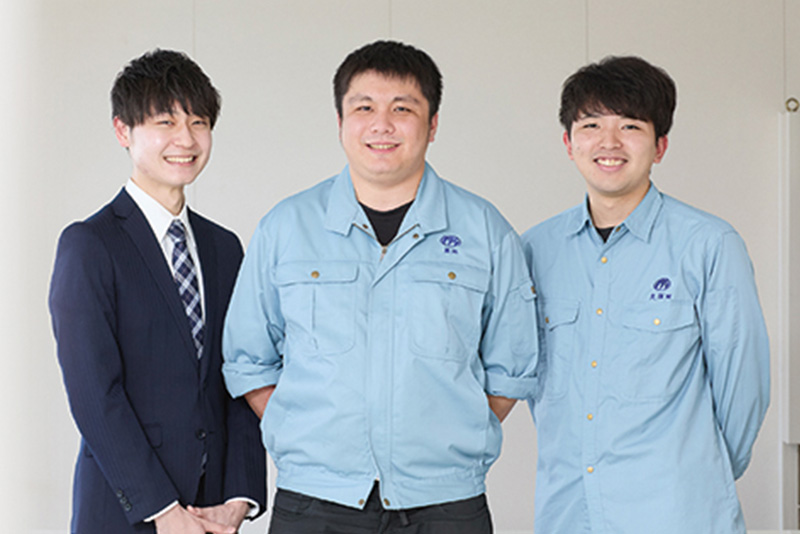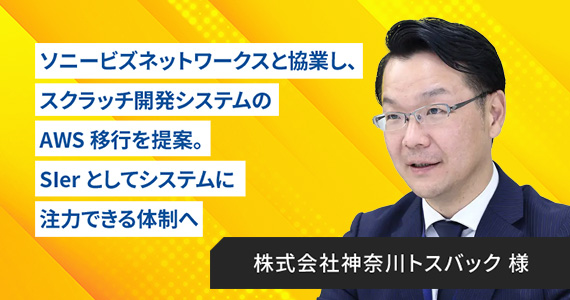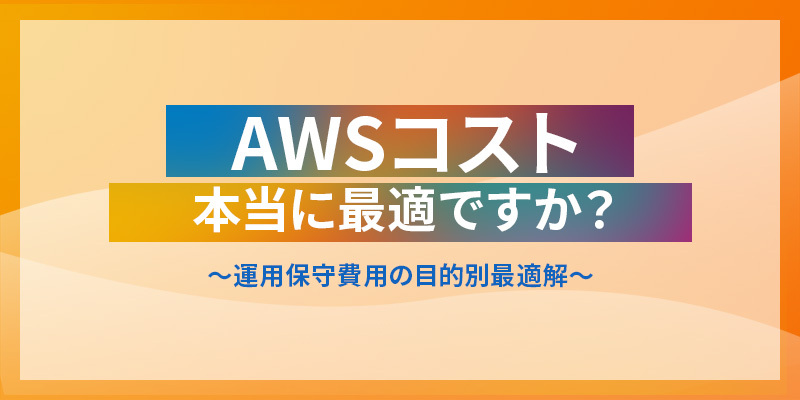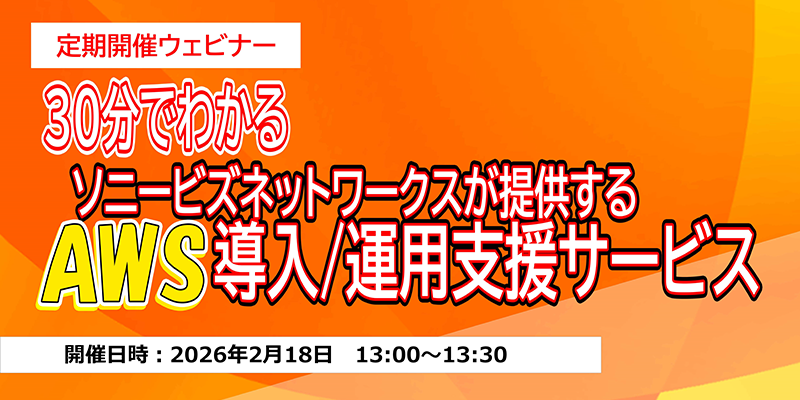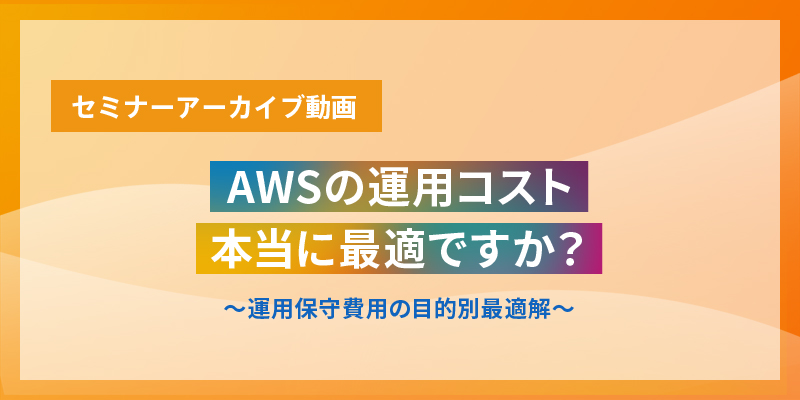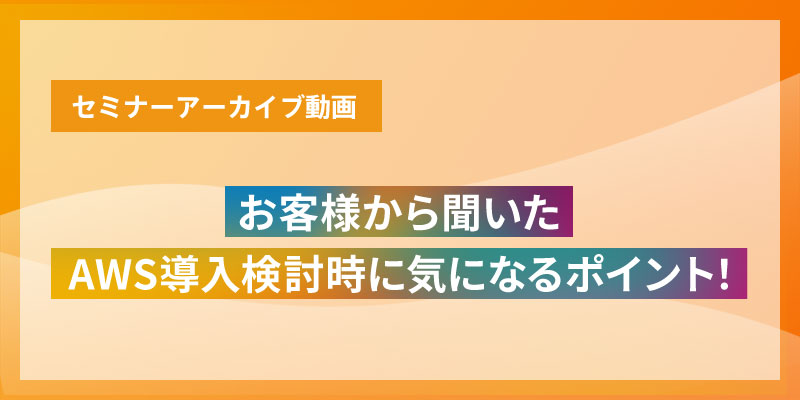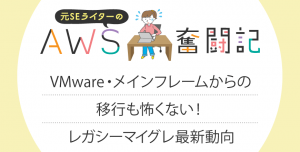VMwareのシステムをAmazon EC2ベースに変換する
まずは、VMware環境の移行支援から。これまでもAmazon QにはJavaのバージョンを変換するコード変換機能を提供していましたが、AWS re:Invent 2024でVMware環境の変換に対応したことが発表されました。VMwareベースで動いていたシステムをAmazon EC2ベースのシステムに変換するのを手伝ってくれる、という機能です。
VMware環境をAWSに移行するとなると、AWSの環境にあわせていろいろ変更することがあります。特にネットワークやセキュリティなど、AWS独特の考え方や設計にあわせなければならず、「既存環境がどうなっているのか」というVMware環境の知識と、「AWSで同じ要件を担保するにはどうすればよいのか」というAWSの知識が必要で、なかなかハードルが高いもの。ここを生成AIで自動化するよ、というのは魅力的に聞こえます。
具体的には、既存環境の情報を集める「インベントリ収集」、移行計画の立案、AWS環境に適したネットワーク設定への変換、物理的なサーバ移行までをカバーし、これをWebベースで一元管理できるのだそう。
VMware環境をAWSに移行するとなると、数年がかりということも珍しくありません。となると、当然予算も結構なことになり、コストがネックで諦める企業もいるでしょう。Amazon Q Developerのこの機能があれば、全部自動でお任せ、とまではいかないかもしれませんが、かなり効率化になることは間違いなさそうです。VMwareから移行するハードルが一気に下がると言ってよいのではないでしょうか。
.NETアプリケーションのLinux化でコスト削減に
レガシーマイグレ、という文脈だとちょっと違うかもしれませんが、.NETアプリケーションの移植を支援する機能もリリースされました。
これは.NET Frameworkアプリケーションを、クロスプラットフォーム .NETに変換するもの。つまり、Windowsでしか使えなかったアプリケーションを、いろいろなOSで使えるようにする、ということで、Linux化すれば最大40%ものライセンスコスト削減になるとされています。40%!なかなかすごい数字です。
さらにこれにより、.NETアプリケーションの移植作業が最大4倍高速化される、と謳っています。そもそも手作業でやるとどれくらい時間がかかるのかが分からないので何とも言えませんが、AWSブログによると、Amazon Q Developerの画面で変換元のソースコードを指定するだけで、自動で新しいバージョンに変換してくれるようなので、これはかなり楽になるのでは、と感じています。
メインフレームのモダナイゼーションも支援
次はメインフレームですが、いやいやさすがに大変でしょ?無理でしょ?どれだけ大がかりな移行なのよ?という気分ではありますが、やれるらしい。
具体的にどう進めるのかというと、まずは既存のコードを解析、ドキュメント化。このあたりは分かりやすいですね。そしてアプリケーション資産を自動で分類・整理したうえで、移行計画を作成してくれると。あとは、COBOLコードをJavaに自動で変換する機能もある、というので、確かにひと通りカバーはされていそうな気がします。
COBOL・メインフレームといったレガシー資産はこのまま塩漬けにするとしても、完全に放置とはいかず、どうするのか悩ましいところです。ほかのシステムと柔軟に連携するためにも、モダナイゼーションしたいニーズはありそうですし、こちらもやはり生成AIでコストを下げられるならぜひ、と期待する企業もあるのではないでしょうか。
Amazon Q Developerの開発支援機能にも注目
これらは移行を直接支援する機能ではありませんが、Amazon Q Developerはエンジニアの開発を支援する機能もかなり充実しています。イベントレポートのコラムで紹介したソニービズネットワークス・濱田さんのセッションでも話があったところですね。
ここまでは、Amazon Q Developerのコード変換機能を紹介してきましたが、そもそもAmazon Q Developerは開発のライフサイクル全般をスコープにさまざまな機能を提供するもの。というわけで、AWS re:Invent 2024で発表された3つの注目機能を紹介しましょう!
●ユニットテスト自動生成
コードからテストを自動で生成します。漏れのないテスト項目を作成できて、品質向上につながります。
●コードレビュー
こちらもそのままですね、指定したソースコードのコードレビューを実行してくれる機能です。「脆弱性がある」などのリスクを見つけて指摘するのとあわせて、修正案も提示してくれるすぐれもの。
●ドキュメント生成
ソースコードから、アプリケーションの概要やリポジトリ構成、データのやり取り、利用しているコンポーネントの解説など、必要なドキュメントを自動で生成します。必要だけど面倒なドキュメント作成を生成AIに任せられるメリットは大きいのでは。
こういった機能をうまく使えば、エンジニアがコーディングなどに集中できて開発を効率化できるはず。つまり、開発工数を削減できて、コストを削減できる、ということ。エンジニアの仕事というと、なんとなくプログラミング(=ソースコードを書いている)のイメージが強いですが、実際プログラミングはごく一部で、そのレビューをしたり、テストしたり、ドキュメント書いたりとかも結構多いもの。そのあたりを自動化するというのは、かなり期待できそうです。
レガシーシステムの移行も加速しそう?今後も注目
生成AI活用は、もはや「今あるデータとどう連携させて活かすのか」がセットで語られるようになっており、となると、レガシーシステムとどう連携するのか、どう活かすのかという話になり、どうマイグレーションするのか……になっていくはず。
VMwareは特に昨年の買収からライセンス体系の変更までいろいろと騒がしいところもあり、移行も含めていろいろ考える企業もいるのではないでしょうか。もちろんそのなかでAWSは有力な候補でしょうし、今回紹介した生成AIの各種機能(あっちもこっちも生成AIでややこしいですね)は移行の後押しになりそうです。この領域は今後も注目ですね。
もちろんですが、「オンプレミスにあるこんなシステム、AWSに移行できるの?」みたいなご相談もソニービズネットワークスにぜひお気軽にお問い合わせください。以上、シイノキでした!
お役立ち資料をダウンロード
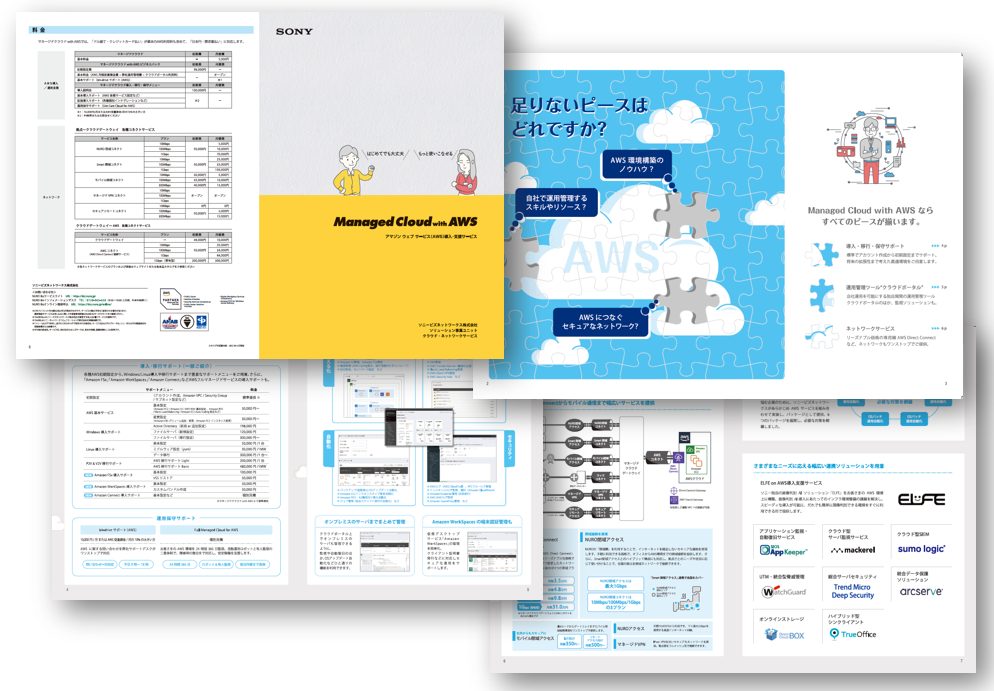
「マネージドクラウド with AWS カタログ」のダウンロードをご希望のお客様は、
以下必要事項をご入力ください。